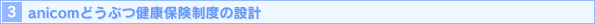 |
|
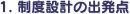 |
|
実際の事業化に際しては、まず、これまでの失敗事例を徹底的に検討することから行われています。また、現存事業者の運営状況の分析も事業化の大きな指針となっています。特に、動物保険制度においては、そのニーズがとても高いため、通常、一定以上の広告宣伝経費を負担できる能力があれば、瞬間的には加入者を獲得することが可能となっていますが、次年度以降も当該保険制度を継続されるケースがとても低く、せっかく動物保険制度にご加入されながら、その内容に不満を感じられ、それ以降継続されないケースが散見されていることが判明しました。
これまでの動物保険制度の内容に対するこれらの不満足を分析いたしますと、次の3つに集約されます。
|
|
 |
|
|
これまでの動物保険制度では、皮膚病、外耳炎、膿瘍、耳血腫といった罹患確率が高いものが対象外であったため、実際の給付金支払時にもめるなど、不満足の原因となっていました。
|
|
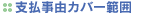 |
|
|
通常、保険制度においては、通院・入院・手術に分別して給付金を支払うことが多くなっていますが、この支払事由を、人間の保険同様に入院・手術に重点を置いたものが多くありました。動物医療においては、通院治療のウェイトが極めて高いにも関わらず、通院が支払対象外であったり、5日以上の通院でなければ対象とならなかったりしていたため不満足を生んでいました。
|
|
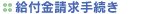 |
|
|
通常の保険制度においては、自動車保険や火災保険を見てもそうなのですが、給付を受けるためには加入者自身が、事故を立証し、給付額を請求するための書類を準備し、保険会社に送ることが必要です。当然動物保険においても、これまでの加入者自身が請求手続きを行うパターンで運営されてきましたが、飼い主様の真のニーズと異なっていたと考えられています。つまり、飼い主様が口にする動物保険があればとの動物保険とは、自動車保険や火災保険のようなものではなく、ヒトの健康保険のようなものであり、保険証を病院に持って行けばそれで、保険診療を受けることが出来、自分自身では何もしなくても良い、飼い主様にとってとても都合が良いものを想定していたということです。このギャップが不満足を生んでいました。
|
|
新たな動物保険制度を事業化するためには、少なくとも、これらの不満足要因をクリアする必要があります。つまり、保障範囲を広げフルカバー化し、ヒトの健康保険のタイプに近づけるということです。 |